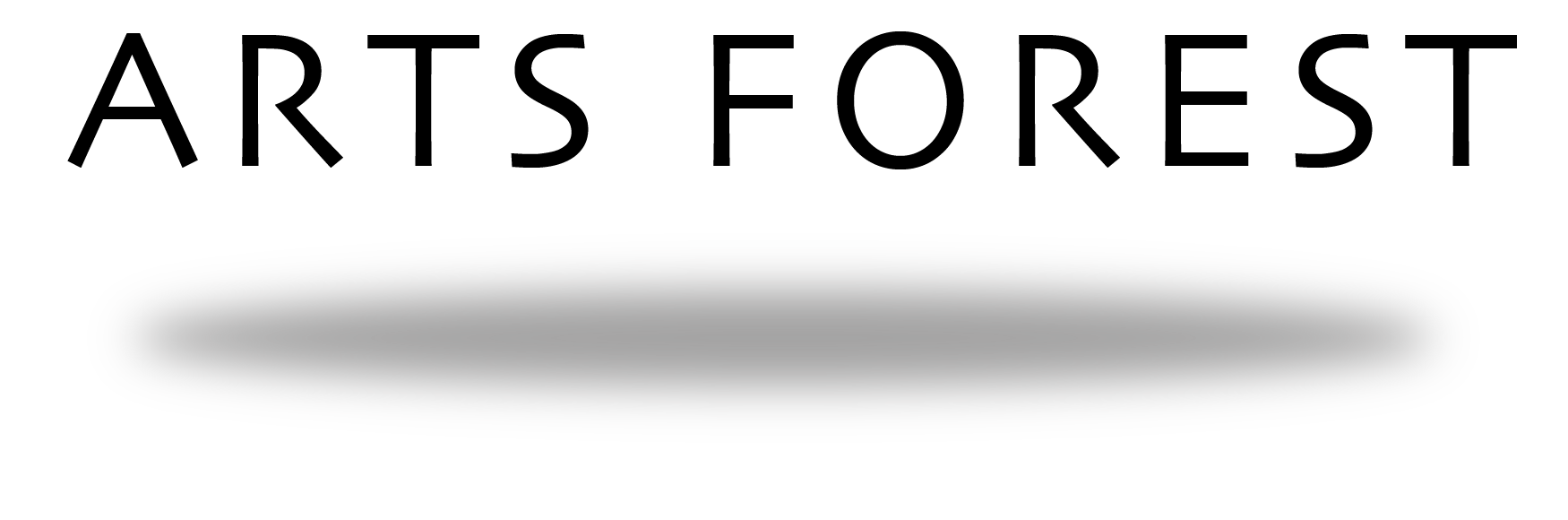視覚情報を中心とした、博物館や美術館。
であれば、聞こえなくても情報を得るには、何ら問題ないはず。
と考えられているようです。
はたして、本当にそうでしょうか。
聴覚とミュージアム
音の聞こえ方は、人によって違いがあります。
生まれながらに聞こえにくい方、病気やケガで聴こえにくくなった方、
そして誰でも程度の違いはあれ年齢とともに聞こえにくくなります。
聴覚に障害があり、魚類学者、博物館学学者でもある鈴木克美は、
合理的配慮の調査のために、彫刻美術館を訪れた時の感想を以下のように述べています。
「聴覚障害者に対しては、博物館サイドのこうした研究も、具体的な対応も、援助もほとんどないことが、改めてわかった。何をしたらいいのかわからないというのが一つ。それにもまして、障害者側からの利用要求がまったくないと。ある程度予想していたこととはいえ、ショックだった」
特定非営利活動法人みみより会 機関誌『みみより』2000年No.12 より抜粋
鈴木は、いったい何を憂いていたのでしょうか。
それを知るためには、聴覚障害のことについて知る必要があります。

聴覚障害

聞こえない人は、音が小さく聞こえるんですよね?



それだけではないんです。
聞こえ方は人それぞれ、みんな違うんですよ。
一言に聴覚障害といっても、その内容は様々です。
難聴の種類には、大きく以下のような分類がされています。
- 伝音性難聴
外耳または中耳の損傷によって音の振動が内耳(蝸牛)に伝わりにくい。
耳を塞がれたようなこもり音として全体的に小さく聞こえる。 - 感音性難聴
音を感じ取る器官である内耳(蝸牛)または聴神経に障害がある。
小さく聞こえるほか、聞こえる周波数(音の高さ)にばらつきがある。 - 複合性難聴
伝音性と感音性の複合。 - 高音域難聴
高音域が聞こえない。加齢による場合も多い。
補聴器



補聴器を使っている方は見たことがあります。
音を大きくする機械ですね?



おしい!大きくするだけではないんです
補聴器は、単に音を大きくするものではなく、使う人の聞こえ方によって細かく調整されています。
なので、補聴器を付けた方の近くでは、決して大きな声や物音を立ててはいけません。
補聴器は、高価な医療機器なので、忘れ物として拾得したら、必ず交番と補聴器取扱い店に連絡してください。
また、補聴器を使っているからと言って、すべての音や声を聞き取れるわけではありません。
補聴器を使っている方と話すときは、いつもより表情を豊かに、そしてゆっくり目に話しましょう。
日本語修得



聞こえないだけだから、読み書きは問題ないですよね?



声を出して話す「発話」の訓練をされた方は問題ない場合が多いです。
でも、手話を中心として生活されている方は、読み書きが得意でない方もいらっしゃいます。
障害がいつ生じたかによって、言語習得の方法が異なります。
- 先天性難聴(ネイティブサイナー)
生まれたとき、あるいは生後まもなくから難聴の症状がある。
言語習得は、手話やイメージによって行われる。
発話や文章を読む能力の修得には、高度な訓練が必要な場合がある。 - 中途失聴
病気やケガなどで、聴力が低下する。
発話言語を習得している場合が多く、文章を読んだり書いたりすることに不自由がない人が多い。



ろう学校で、読み書きや発話の訓練をされると思ってました。



残存聴力を活かして、発話の訓練を中心にする学校と、発話よりも手話での勉強に重点を置く学校があります。
手話という言語



手話が言語?
手話って日本語を手指で表現するものですよね?
手話は、表現方法のことではないのですか?



手話には、表現方法だけでなく、そこには文化も含まれています。
近年、手話を言語として、すなわち文化として認めようという動きが全国に広がりつつあります。
2013年、鳥取県は、日本で初めて手話言語条例が施行されました。
それから遅れること9年、2022年に東京都も手話言語条例を施行しました。
鳥取県は、条例制定の目的を以下のように規定しています。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し基本理念を定 め、県、市町村、県民及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話の普及の ための施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者とろう者 以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。
(手話の意義)
第2条 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな社 会生活を営むために大切に受け継いできたものであることを理解しなければならない。
手話は、日本語や英語、フランス語と同様の「言語」であることを大前提にしています。
ろう者さんが使ってきた日本独自の手話を「日本手話」、聴者の話しことばをそのままの語順で表現した手話を「日本語対応手話」といいます。
日本語対応手話は、日本語そのものを修得していなければ、読解が難しく、高齢のろう者さんや、発話を使わないろう者さんにとっては、わかりにくい手話です。
日本手話は、日本語とは語順が異なり、英語に近い語順で表します。
また、曖昧な表現は少なく、助詞はあまり意識しません。
例えば、「電車に乗る」、「電車が乗る」、「電車で乗る」、「電車を乗る」などの表現は「電車」+「乗る」だけで表現します。
そのため、日本手話の会話はとてもスピーディで、初学者が読み取ることはなかなか難しい手話です。
手話には、その他にも国際手話や、その国ごとの手話があり、日本の手話にもその地方でしか通じない「方言」があります。
文字情報
「聴覚障害者は、耳が聞こえなくても、眼で見るのに不自由はないし、行動にも困らないのだろう。とすれば、『観察の場』である博物館で、なぜ、障害者としての対応が必要なのかという声もあった。言語習得以前に聴覚を失ったろうあ者に、博物館の解説を読むのが困難という事情も、ほとんど知らない。」
特定非営利活動法人みみより会 機関誌『みみより』2000年No.12 より抜粋 )
聞こえにくくても、文章なら問題なく読める、と思われることが多いようです。
しかし、生まれながらにして聞こえにくいある方と、病気やケガで聞こえにくくなった中途失聴の方、また発話(声を出して話す)を使うか使わないか、によって文章の受け入れ方には大きな違いがあります。
発話の訓練をされた方や、中途失聴の方の多くは、長い文章でも難なく使いこなされます。
しかし、生まれた時から聞こえにくい方や、幼い時に失聴された方、発話を使わない方の中には、長い文章が苦手な方も少なくありません。その場合、書くことも得意とされないこともあります。
都内のある美術館で開催された大規模企画展で、音声ガイドの台本が¥500で貸し出しされました。しかし、聞こえにくい方にとって、話し言葉をそのまま活字にした文章は非常に難解なものでした。
できれば、ガイドブックやキャプション、ゾーンキャプションなども、平易な日本語と短い文章を心がけることで、聞こえにくい方だけでなく、外国語を母国語とする人や高齢者にも理解が深まると思います。
コミュニケーション



聞こえない方ともお話ししたいけど、
手話を知らないからな〜



手話は聞こえない方とのコミュニケーション方法の
ひとつですが、それだけではありませんよ。
聞こえない方や難聴の方とコミュニケーションするには、手話はひとつの方法です。
しかし他にも、空中や手のひらに文字を書く「空書き」、筆談ボード、コミュニケーションボード、唇の形で言葉を読む、読唇ができるろう者さんも多くいらっしゃいます。このように手話以外でも、コミュニケーションをとることは十分に可能です。
声を使わないコミュニケーションでは、顔の表情、表現の勢い、などにも重要な意味が含まれています。
そのため、マスクが一般的になった昨今では、ろう者さんはコミュニケーションに大変苦労されています。
マスク越しのコミュニケーションは、いつもより2倍増しの笑顔でお願いします!